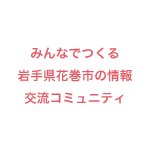初七日(8月4日)、三十五日(9月1日)、四十九日(9月15日)…。市議引退後の改選花巻市議選の投開票日のその日(7月29日)に妻が急逝してから、節目の忌日(きにち)があっという間に過ぎ去り、目の前には百ヶ日(11月5日)が近づいてきた。仏教ではこの日を「「卒哭忌」(そっこくき)と呼ぶ。「哭」は嘆き悲しむこと、「卒」は終わること…。「どんなに親しい人が亡くなっても、嘆き悲しむのは百ヶ日で終わりにする」という意味だという。「仏式というやつは随分と押しつけがましい。こころの区切りをつけるのはこっち」―。亡骸(遺骨)のそばで寝起きしながら、「喪失感」という得体のしれない気持ちに打ちのめされていた、そんなある日―。
「がんの宣告」―。妻の身の回りを整理しているうちにパンフレットから一枚の紙片がすべり落ちてきた。CT検査(コンピュタ−断層撮影)とPET検査(陽電子放射断層撮影)の結果、ステ−ジ4(末期)の肺がんが見つかったことが記されていた。日付は2014年6月9日、旅立つ4年前の手書きのメモだった。この時期、私自身は2期目の市議選への出馬準備で大わらわだった。重い病を抱えることになった妻はそれでも「頑張ってね」と裏方に徹した。私は当然、医者から告げられて知っていたが、そのメモが「散骨」関係のパンフレットに挟まっていたことにびっくりした。「お墓もないし、死んだら散骨か樹木葬がいいね」と生前、話していた。散骨の資料収集はがんを宣告された以降に集中していた。秘かに死出の旅支度をしていたことに胸を締め付けられた。「あの時、出馬を止めておけば…」―
たとえば、こんな姿を懐かしく思い出す。沖縄・石垣島に住むたった一人の娘夫婦と2人の孫たちのことを一時も忘れることがなかった。死の直前、介護に駆けつけた娘が台所の整理をしていて悲鳴を上げた。買いだめした品々があちこちから出現したからである。そういえば、夜中にゴソゴソと孫たち宛ての宅急便の詰め込みをしていた現場を何度も目撃した。「(沖縄)八重山諸島」での散骨を紹介するパンフレットに「第一候補」とシールが貼ってあった。「あのメモはひょっとして、孫たちのそばに行きたいという遺書だったのかもしれない。そうだ、サンゴ礁の海へ」とそう思った刹那(せつな)、もうひとつの「卒哭忌」の光景が目の前にせりあがってきた。
「まだ遺骨のひとかけらも見つかっていません。だから、3人の生死は誰にも分かりません。もう死んでいるかもしれないし、あるいはまだ生きているかもしれない。そう思うしかないと自分に言い聞かせているんです」―。東日本大震災から百日目の2011年6月18日、三陸沿岸の大槌町で犠牲になった人たちの合同慰霊祭があった。779人のうち、前日までに死亡届が提出された567人の名前と年齢がひとりずつ読み上げられた。母親と妻、それに愛娘の3人が行方不明のままの白銀照男さん(9月14日付当ブログ「『四十九日』と魂の行方」参照)は「名前が呼ばれないのを喜んだら良いものか…」と無言のまま、会場をあとにした。白銀さんが3人の死亡届を役所に持って行ったのは、その2週間後のことである。
「あんたは奥さんと一緒にいられるだけ幸せじゃないか」―と白銀さんに背中を押されたような気持になった。ある日突然、目の前から消えた肉親に自らが死を宣告しなければならない残酷さに体が震えた。「もう、泣き悲しむのは止めにせよ」という仏(ほとけ)の説法の酷(むご)さにも戦(おのの))いてしまった。その一方で、「おまえの喪失感って、一体なにほどなのか」という声が遠音に聞こえたような気がした。私は11月中旬、迎えにくる娘と一緒に妻の亡骸を背中に背負って、石垣島に向かおうと思っている。「卒哭」のためではなく、より多くの死と悲しみを共有することができるように…
(写真は故人が好きだった花々と一緒に海へ眠る散骨風景=インタ−ネット上に公開のイメ−ジ写真から)