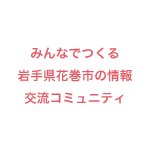ハ−ドカバ−のその可愛らしい詩集は妻が母親から譲り受けた、古ぼけた岩谷堂タンスの一番下にまるで隠すようにしてあった。表題の原作が『最後だとわかっていたなら』(佐川睦訳)というタイトルで翻訳されたのは11年前。米国人女性のノ−マ・コ−ネット・マレックさんが亡き息子に捧げた詩で、1989年に発表された。「9・11」(2001年)の米国の同時多発テロを機にチェ−ンメ−ルで世界中に広がり、日本では「3・11」(2011年)の東日本大震災後のわずか半年間で16刷を重ねるヒット作となった。さらに、震災6周年の昨年の3月11日、地元紙「岩手日報」が詩の全文を掲載するなど犠牲者の死を悼(いた)む詩として、その輪はさらに広がった。
「あなたが眠りにつくのを見るのが、最後だとわかっていたら/わたしはもっとちゃんとカバ−をかけて/神様にその魂を守ってくださるように祈っただろう」―。詩集はこんな書き出しで始まる。あの日の光景が目の前によみがえった。妻はベットから転げ落ちるようにして死んでいた。私が発見したのは死後4時間もたってからだった。「最後だとわかっていたら」…そばにいてやれなかったことを今さらのように悔(く)いた。それにしても妻はなぜ、この本を秘かに手に入れ、タンスの奥にしまい込んでいたのか。作者のマレックさんは末期がんをわずらい、2004年に64歳で他界している。当然、震災犠牲者への鎮魂がまず、あったのだと思う、と同時に、同じ病を抱える妻が死期を悟った時の気持ちをこの詩に重ねたのではないのか。そして、私に心配をかけまいと…
「お元気ですか。おばあちゃんがいなくても、ぼくたちがついてます。げんきに長生きしてください。フレ−、フレ−、がんばれ」―。敬老の日、沖縄・石垣島に住む二人の孫から葉書が届いた。妻が亡くなった時、孫たちは7歳と9歳だった。この「死」の現実に対し、どう向き合わせたらよいのか…母親である娘にも私自身にも少しの迷いがあった。私はそっと、二人の背中を押した。「おばあちゃん…」と小声で呼びかけ、二人は冷たくなった妻のひたいに手を当てた。口を真一文字に結んだ頬に、ポロリと涙のひとしずくが伝って流れていた。ひとつの「儀式」が終わったのだと私は思った。翌日の収骨の際、二人は競うようにして、骨を拾っていた。「おばあちゃんがいなくても…」―、孫たちがそのことの意味に自分たちなりに折り合いをつけ、納得してくれたと思った。
妻の死の約3週間前の7月6日、オウム真理教の元代表、松本智津夫(教祖名、麻原彰晃)死刑囚ら7人の元教団幹部に対する死刑が執行された。死刑前夜でしかも豪雨災害のさ中、安倍晋三首相や執行責任者の上川陽子・法相(当時)ら自民党議員がにこやかに乾杯している写真がネット上に出回った(7月7日付当ブログ参照)。この狂乱じみた光景について、作家の辺見庸さんは「祝祭」になぞらえて、こう書いた。
「死刑の光景は日本において不可視であるがゆえに、かえって幻想のスペクタクル(見世物)となり、無意識のうさ晴らし(娯楽)と化してはいないだろうか。だとすれば、この国はすでに人間の『つつしみ』というものがなにかを忘れ、倫理の根源に悖(もと)るゾ−ンに足をふみいれつつある。すなわち、日本はみように晴れやかに危うい一線をこえたのだ。…サッカ−の試合後、日本人サポ−タ−たちがみんなで会場のゴミ拾いをしたという公徳心の高さと、絞首刑の国民的受容にはどのような道徳的なバランスがたもたれているのか。不可思議である」(7月14日付「岩手日報」)
「『ごめんね』や『許してね』や『ありがとう』や『気にしないで』を伝える時を持とう/そうすれば、もし明日が来ないとしても/あなたは今日を後悔しないだろうから」―。マレックさんの詩はこう結ばれている。考えて見れば、私は妻の生前にこうした言葉のひとかけらでも口にしたことがあったろうか。おそらく、なかった。「後悔、先に立たず」―を地で行くような人生だったとつくづく思う。私はこの詩集を「おばあちゃんの遺品」として、孫たちに送ろうと思っている。「死」がだんだんと遠ざけられ、あろうことか「祝祭」にまつり上げられるという狂気の時代を、これから先、生きていかなければならない幼い孫たちの「転ばぬ先の杖」として…。
(写真は妻の遺影の前に立つ、向かって右が長男の主水(=もんど、現在10歳)と次男のるん太(8歳)=2018年8月1日、花巻市内の斎場で)