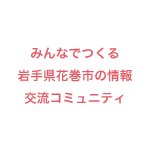「バンバンバン、ゴキッ…」―。今から50年近く前、夕闇が迫ると同時に転勤先の新聞社の支局の庭先から耳慣れない音が聞こえてきた。1963(昭和38)年11月9日、死者458人という戦後最大の炭鉱事故(炭じん爆発)を起こした三池炭鉱を有する炭都―福岡県大牟田市は東北生まれの妻にとっては、“異界”にまぎれこんだような気持だったのかもしれない。加えて、産後間もない身にとって、この不気味な音は心身にこたえたようだった。すぐ隣がラ−メン店だった。夫婦二人で切り盛りする店は行列ができるほどの繁盛ぶりだった。妻がのちに「九州のお母さん」と呼ぶようになる奥さんに恐るおそる尋ねてみた。「ああ、あれは骨割りの音たい。そういえば、東北には豚骨ラ−メンはなかもんね」
一人娘は1年半が過ぎても足が立たなかった。信心深い奥さんが一生に一度、願いごとがかなうという高塚愛宕地蔵尊(大分県日田市)に連れて行ってくれた。お参りをし、近くの土産物店で一休みしていた時だった。娘が突然、おもちゃの陳列棚に向かってとことこと歩み寄った。「歩いたばい。願いごとばかなったばい」―。店内は大騒ぎになり、妻は娘に頬ずりをしながら、大粒の涙を流した。以来、娘は見違えるように元気になった。出前のドンブリを回収する軽自動車の隣にちょこんと座り、店に戻ると豚骨のあぶらが浮いたラ−メンのス−プをのどを鳴らしながら、飲み干すようになった。
店の名前は「福竜軒」―。炭じん爆発事故の約1か月半前にオ−プンした。爆発があった三川鉱からは随分離れていたが、店の窓ガラスががたがた揺れた。「恐ろしかったとよ。ガスを吸った人もたくさんおらした」。私が赴任した当時、爆発事故で一酸化炭素(CO)中毒という不治の病を背負わされた患者・家族が絶望的な闘病生活と補償要求の運動を続けていた。労災認定された患者だけで、839人に上った。炭住街をくまなく回り、患者の訴えを聞く日々。疲れた体を直してくれるのも一杯の豚骨ラ−メンとごま塩を振りかけたおにぎりだった。
1965(昭和40)年の夏の甲子園大会で、政治犯などを収容した「三池集治監」跡に建つ県立三池工業高校が初出場で全国優勝を果たすという偉業を打ち立てた。この時、チ−ムを率いたのが名将の誉れ高い故・原貢監督。子息の辰徳さん(60)は今回、3度目の巨人軍の監督に就任することが決まった。この野球親子がここの豚骨ラ−メンをすすり、当時まだ小学校低学年だった辰徳さんが野球練習の球拾いをしていた姿を懐かしく思い出す。娘が大学を卒業後、50CCバイクを乗り継いで、沖縄・九州、四国を1周したことがあった。その途次、電話がかかってきた。「久しぶりに食べたちゅより、飲んだよ。うまかった」。娘が現在に至るまで病気知らずでいられるのも、そして、原新監督を誕生させたエネルギ−源も元をただせば、福竜軒の豚骨ラーメンと何よりも年季の入った「骨割り」ス−プだったにちがいない。
「まだ、信じられなかと。線香を上げるまでは信じられんと」―。今月中旬、「九州のお母さん」こと、池田ツナ子さん(77)から電話があった。空港に出迎えると、保育士で一人娘の祥子さん(50)も一緒だった。手土産に妻の好物だった地元の菓子「草木饅頭」と亡くなるまで欠かさなかった福岡産の「八女茶」を携えていた。「たった二つしか違わないとにお母さんって。でも、うれしか。ずっと、身内みたいだった。そういえば、美恵子さん(妻)は濃うかお茶ば好いとらしたけん…」。ツヤ子さんはこう言って、入れたてのお茶を仏壇に供えて手を合わせた。並んで座った祥子さんが口を添えた。「ラ−メンが繁盛したのは良かばってん、私のご飯を作る暇もなくって…。だから、いつもおばちゃんの家で。おばちゃんの、手作りのババロア(洋菓子)の味がいまでも忘れられない」
私は今どきは希薄になりつつある「人間のきずな」の太さに胸が熱くなる思いがした。「いつだったか、スリランカの王様もお忍びで食べに来らしたことがあっとよ」とツル子さんが別れ際に行った。腹がぐぐ〜っと鳴った。沖縄・石垣島での妻の散骨が終わった帰途に必ず、立ち寄ると約束した。「待っとってね」。いつの間にか、舌になじんだ九州弁になっていた。
(宮沢賢治が好きだという二人を「雨ニモマケズ」詩碑に案内した=10月22日、花巻市桜町4丁目で。右は名物の福竜軒の豚骨ラ−メン)