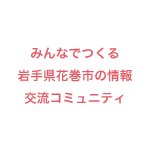白砂のように細かく砕かれた妻の亡骸(なきがら)はまるで、小型のマンタかジュゴンにでも変身したかのようにして、サンゴ礁の海へと静かに消えていった―。今年7月末に旅立った妻(享年75歳)の散骨の儀式が12月1日、娘夫婦と二人の孫が暮らす沖縄・石垣島で行われた。式には東京に住む妹と弟も参列。思い出をつづった折り鶴や好きだった花々などを海に投げ入れ、最後の別れを惜しんだ。
1日午後2時半すぎ、7人を乗せたチャ−タ−船が石垣島最大の名蔵(なぐら)港を出港した。汗ばむほどの快晴。太陽の照り返しがキラキラと反射する。ほぼ、凪(な)ぎ。約20分後、湾外の散骨の現場へ。水溶性の白い袋に詰められたパウダ―状の粉骨があっという間に海水と溶け合い、その部分が白濁色に変わった。波間に揺れる亡骸が一瞬、小型のマンタのような、あるいはジュゴンのような輪郭を刻んだように見えた。その周辺を折り鶴たちが浮き沈みした。妻が亡くなる直前まで聴いていたバロック音楽のCDがセットされ、船内にはパッヘルベル(ドイツの作曲家)のカノンの世界が静かに広がった。
「君が大好きだった沖縄の守り神・シ−サ−を大勢、従えての最後の旅立ち。真っすぐにニライカナイ(黄泉の国)に向かってください」―。私は折り鶴にこう書き、こんな風に結んだ。「孫たちもサンゴ礁の彼方におばあちゃんの化身を見つけ、元気に育ってくれると信じます。ありがとう。そして、さようなら」ー。妻の霊は白雪をいただく故郷の霊峰・早池峰山と、南の島・ニライカナイの海に抱かれながら、永遠(とわ)の眠りについた。本当にこれで終わったんだと思った。
「咳(せき)をしても一人」―。帰路の船の中で、孤高の俳人(尾崎)放哉のあの名句が口をついて出た。そういえば、同じ漂泊の俳人(種田)山頭火にも「鴉(からす)啼(な)いてわたしも一人」という句がある。「独居老人」などというお仕着せがましい言葉ではなく、私は「一人」の思想を考え続けながら、これから先の短い人生を歩んでいこうと思っている。「おばあちゃんは死んだんじゃない。ジュゴンに生まれ変わったんだよ」―。そんな励ましの言葉を口にする孫たちの成長ぶりに、老残のわが身はうれしさのあまりに震えてしまう。
(写真は散骨する私。亡骸はまるで生きているようなマンタかジュゴンの姿に。「自然に還る」とはこのことか、と得心できた気がした=12月1日午後3時ごろ、石垣島・名蔵港の南東約2カイリの海上で)