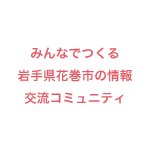テロの銃弾で犠牲になった医師の故中村哲さん(享年73)の告別式が11日、福岡市内の斎場で執り行われ、親族を代表して長男の健さんが「父から学んだこと」という内容の弔辞を読み上げた。人柄が偲ばれる文章なので、以下に全文を掲載する(12日付「西日本新聞」から)
※
この度の父・中村哲の訃報に際し、親族を代表いたしまして、皆様へご挨拶をさせていただきたく存じます。私は故人の長男で健と申します。最初に申し上げたいのは、父を守るために亡くなられたアフガニスタンの運転手の方・警備の方そして残されたご家族・ご親族の方々への追悼の想いです。申し訳ない気持ちでいっぱいです。悔やんでも悔やみきれません。父ももし今この場にいたらきっとそのように思っているはずです。家族を代表し心よりお悔やみを申し上げます。私たち家族は今回の訃報に大きなショックと深い悲しみに苛まれました。しかし、多くの方々がともに悲しんで下さり、私たち家族へ多くの激励の言葉をかけて下さっています。本当に救われています。
上皇様ご夫妻からのご弔意の賜わりをはじめ、いつもそばで父を支えてともに活動して下さり、これからも継続の意向を示してくださっているペシャワール会の皆様、アフガニスタン国での父の活動に賛同しご支援をいただいている大統領をはじめ政府関係の皆様、同じくアフガニスタン国の大変な環境にある作業現場の中で父とともに活動をしていただいているアフガニスタン国の国民の皆様、父の活動にご賛同いただきご支援をいただいている日本の皆様、そして今回の訃報から父を遠い異国に迎えに行くにあたり早急にそして最短の移動スケジュールでいけるようにご配慮していただき、宿泊先まで手配していただいた外務省・大使館・政府関係の職員の皆様、どんなに感謝しても足りません。父が今までもそして命がなくなってもなおアフガニスタンで活動ができるのも偏に皆様のご賛同・ご協力のおかげとしかいえません。
また今回の事件で警察、航空会社、葬儀会社、保険会社に関わる皆様にはいつも私たち家族の気持ち・立場に立っていただいています。そして24時間、どんな時でも真摯な対応をしていただいています。私たち家族は、皆様のおかげで不安・悲しみの気持ちから本当に守られています。感謝しています。生前、父は山、川、植物、昆虫、動物をこの上なく愛する人でした。家ではいつも庭の手入れをしていました。私が子供の頃はよく一緒に山登りに連れて行ってもらいました。最近も、父とはよく一緒に山に登っていました。遊びに行くときは「できればみんなで行こうよ」、「みんなで行った方が楽しいよ」ということを言っていました。みんなと楽しみたいという考えの人でした。
また父がアフガニスタンへ旅立つとき、私と2人きりで話す場面ではいつも「お母さんをよろしく」「家をたのんだ」「まあ何でも一生懸命やったらいいよ」と言っていました。その言葉に、父の家族への気遣い・思いを感じていました。今、思い返すと、父自身も余裕がない時もきっとあったはずです。いつも頭のどこかで家族のことを思ってくれている父でした。父の、自分のことよりも人を思う性格・どんなときも本質をみるという考えから出ていた言葉だったと思います。その言葉どおり背中でみせてくれていました。
私自身が父から学んだことは、家族はもちろん人の思いを大切にすること、物事において本当に必要なことを見極めること、そして必要なことは一生懸命行うということです。私が20歳になる前はいつも怒られていました。「口先だけじゃなくて行動に示せ」と言われていました。「俺は行動しか信じない」と言っていました。父から学んだことは、行動で示したいと思います。この先の人生において自分がどんなに年を取っても父から学んだことをいつも心に残し、生きていきたいと思います。最後に親族を代表致しまして皆々様からの父と私たち家族へのご厚情に深く感謝いたします。
(写真は菊の花に囲まれた故中村さん=11日、福岡市内の斎場で。インターネット上に公開の写真から)
《追記》〜ホームレスの背中を押した故中村さん
アフガニスタンで凶弾に倒れた中村哲医師(73)の言葉は、時に迷いながらも信念を持って活動する人たちの背中を押した。ホームレスを支援するNPO法人「抱樸(ほうぼく)」(北九州市八幡東区)の奥田知志理事長(56)もその一人。新米牧師だった約30年前に出会った際、嫉妬と尊敬の念が入り交じる複雑な感情で接したことを鮮明に覚えているという。舞台は違えど、中村さんの活動に同じ理念を感じてきた奥田さんは10日、「この悲しみを憎しみに変えてはいけない」と訴えた。
中村さんが現地代表を務める福岡市の非政府組織(NGO)「ペシャワール会」が発足した1983年、関西学院大1年だった奥田さんは大阪の釜ケ崎でホームレス支援を始めたばかり。中村さんと初めて出会ったのは90年、北九州市八幡東区の東八幡キリスト教会に赴任した時だった。中村さんも同じキリスト教徒。同教会の信徒たちがペシャワール会を支援しており、中村さんは94年ごろまで同教会で活動報告会を開いていた。
報告会には80人もの支援者が詰め掛け、熱気にあふれていた。中村さんの話には圧倒された。パキスタンで、ハンセン病患者がはだしで歩いて傷を負い、血やうみが流れ出て症状が悪化するのを防ぐために、古タイヤでサンダルを作っているとの内容に、思わず聞き入った。それと比べて自分の活動を支援してくれるのは10人に満たない。「海外の支援は受けがいい。アフガンもいいが、日本の困窮者はどうする」と嫉妬心が頭をもたげた。同時に「病気を癒やすだけでなく、社会自体を変えていく。スケールが大きく、自分にはとてもできないことだと思った」。
中村さんは仰ぎ見るような存在で、独特の「近寄りがたさ」も感じていた。講演会で何度も一緒になったが、短い言葉を交わす程度。2人で話し込むような機会はなかったが、その言葉は深く心に刻み込まれている。「生き方、言葉が僕の活動の励みだった」中村さんは報告会や講演会で、ペシャワール会の「誰も行かぬなら、我々が行く」という理念を繰り返し訴えた。ホームレス支援を始めた当初、奥田さんは「そんな支援に何の意味があるんですか」とよく聞かれた。ホームレスは「無に等しい存在」で誰も目を向けない。自分と中村さんの活動を重ね、通じるものを感じていたという。
「頑張ってますか」。2016年9月、福岡市で開かれた講演会で一緒になり、そう声を掛けられた。中村さんの講演をじっくり聞いたのは、この時が最後になった。奥田さんは今、中村さんの死をこう受け止める。「中村先生は復讐(ふくしゅう)してくれとは言わない人だとみんな確信している。中村哲という人は、自分の命が、次の命につながっていくことを望んでいると思う。この悲しみを自分の生き方にどう生かしていくか。僕はどこに行くべきか考えていきたい」(12日付「西日本新聞」)