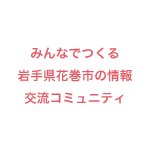振り返ってみれば、あっという間に接近されたような気がする。「六次のへだたり」理論が本当かどうか、僕は知らない。知りあいのつてをたどっていくと、驚くほどわずかな人数を介しただけで世界の誰とでもつながってしまうという、あの話だ。でも今度のウイルスは、まるで網の目をたどる昆虫のように、そんなひとの縁(えん)の連鎖によじ登り、僕たちのもとにたどり着いた。中国にいたはずの感染症が次はイタリアに来て、僕らの町に来て、やがて誰か著名人に陽性反応が出て、僕らの友だちのひとりが感染して、僕らの住んでいるアパ−トの住民が入院した。
その間、わずか30日。そうしたステップのひとつひとつを目撃するたび―確率的には妥当で、ごく当たり前なはずの出来事なのに―僕らは目をみはった。信じられなかったのだ。「まさかの事態」の領域で動き回ることこそ、始めから今度のウイルスの強みだった。僕らは「まさか」をこれでもかと繰り返した末に、自宅に閉じこめられ、買い物に行くために警察に見せる外出理由証明書をプリントアウトする羽目となった。義憤、遅れ、無駄な議論、よく考えもせずに付けたハッシュタグ―そのひとつひとつが、約17日後に、死者を生む原因となった。なぜなら感染症流行時は、躊躇(ちゅうちょ)をしたぶんだけ、その代価を犠牲者数で支払うものと相場が決まっているからだ。僕らがかつて味わったなかで、もっとも残酷な時間単価だ。
イタリアの死者数は中国のそれを超えた。僕たちは一連の偶発的原因に怒って当然だし、怒るべきだが、問題の根本のところで必ず、自分たちが「まさかの事態」を受け入れるのが不得手な国民であるという事実に直面してしまうはずだ。これは近年、他の似たような感染症流行を経験済みだった国々と比較しての話だ。いずれにしてもここまでくると、僕らにしても、この「まさかの事態」の前進が、今日終わることもなければ、全国民の外出制限を指示した首相令の期限が切れる4月3日に終わることもないとわかっているはずだ(2020年4月5日現在、期限は4月13日まで延長されている)。それは自宅隔離の指示が解かれても終わらず、今回のパンデミック自体が終結しても終わらないだろう。「まさかの事態」はまだ始まったばかりで、ここには長く居座るつもりでいるはずだ。もしかするとそれは、僕らの前に開かれようとしている新たな時代の特徴となるのかもしれない。
戦争という言葉の濫用について書いているうちに、マルグリット・デュラスの言葉をひとつ思い出した。逆説的なその言葉はこうだ。「平和の様相はすでに現れてきている。到来するのは闇夜のようでもあり、また忘却の始まりでもある」(『苦悩』田中倫郎訳 河出書房新社)。戦争が終わると、誰もが一切を急いで忘れようとするが、病気にも似たようなことが起きる。
苦しみは僕たちを普段であればぼやけて見えない真実に触れさせ、物事の優先順位を見直させ、現在という時間が本来の大きさを取り戻した、そんな印象さえ与えるのに、病気が治ったとたん、そうした天啓はたちまち煙と化してしまうものだ。僕たちは今、地球規模の病気にかかっている最中であり、パンデミックが僕らの文明をレントゲンにかけているところだ。真実の数々が浮かび上がりつつあるが、そのいずれも流行の終焉とともに消えてなくなることだろう。もしも、僕らが今すぐそれを記憶に留めぬ限りは。
だから、緊急事態に苦しみながらも僕らは―それだけでも、数字に証言、ツイ−トに法令、とてつもない恐怖で、十分に頭がいっぱいだが―今までとは違った思考をしてみるための空間を確保しなくてはいけない。30日前であったならば、そのあまりの素朴さに僕らも苦笑していたであろう、壮大な問いの数々を今、あえてするために。たとえばこんな問いだ。すべてが終わった時、本当に僕たちは以前とまったく同じ世界を再現したいのだろうか。
僕らはCVID−19の目には見えない伝染経路を探している。しかし、それに輪をかけてつかみどころのない伝染経路が何本も存在する。世界でも、イタリアでも、状況をここまで悪化させた原因の経路だ。そちらの経路も探さなくてはいけない。だから僕は今、忘れたくない物事のリストをひとつ作っている。リストは毎日、少しずつ伸びていく。誰もがそれぞれのリストを作るべきだと思う。そして平穏な時が帰ってきたら、互いのリストを取り出して見比べ、そこに共通の項目があるかどうか、そのために何かできることはないか考えてみるのがいい。
(写真は全土がロックダウン(都市封鎖)されたイタリア。マンションに閉じ込められた夫婦は不安気に外を眺めていた=3月中旬、ロ−マ市内で。インタ−ネット上に公開の写真から)
《追記−1》〜「コロナ戦争」への異議!?フランス人哲学者、クレ−ル・マランからのメッセ−ジ
「私の感覚では、戦争ではありません。敵がいないのですから。私たちが直面しているのは生命の掟に刻まれている現象であり、それは創造と破壊両方のプロセスを通じて現れてくるものなのです。病気というのは、退化や死と同様、生物学的な意味で生命の一部です。人間的な知能や害を加えるという意志がない場合、敵は存在しません。病気を戦争のモデルによって考えることは流行っていますが、生命の本質を見誤っています。コロナウイルスをイメ−ジしたりその作用を理解したりするために、戦争のように考えることが役に立つとは思いません。いま大切なのは対峙することではなく、むしろパンチを返さない俊敏なボクサ−のように回避することが重要なのですから、なおさらです」(「ク−リエ・ジャポン」4月8日号)
《追記―2》〜「リスクとの共生」…思想家、内田樹さんからのメッセ−ジ
「もう勝てないと分かったら、『負け幅』をどうやって小さく収めるかを考える。プランAが破綻したら、すかさず次善の策であるプランBに切り替える。たぶん英語圏にはそういう文化があり、日本にはない。日本政府は『水際作戦』の成功と東京五輪の成功を夢見て、『最悪の事態』に備えることをしなかった。これを無能・無策と謗(そし)る人が多いが、統治者一人の責任に帰すのは気の毒だと思う。日本人というのは総じて『そういう人たち』だからである。ウイルス相手に人間の側に『勝ち』はない。できるのは、『負け幅』を減らすことだけである。でも、わが国には『負け幅を減らす』ための知恵や工夫を評価する文化がない。それを認めるところからしか『次』は始まらない」(『週刊金曜日』5月1日&8日合併号)