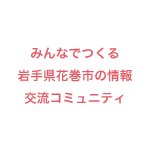コロナ禍がもたらした自粛ム−ドや同調圧力が強まる中、こうした風潮に異議申し立てをする“言論”が影を潜めつつある。こんな時にこそ、出番が期待される作家の辺見庸さん(75)の肉声を久しぶりに聞いた。NHKEテレ(6月7日放映「こころの時代―緊急事態宣言の日々に」)に登場した、歯に衣着せぬ“毒舌”は相変わらず健在だった。「カオス(混沌)のいまこそ、言葉の復権を」…聖書から映画、東西の知性(注記参照)を動員した洞察は鋭利な刃物で時代の闇を切り裂く凄みさえ感じさせた。しかし、私はむしろその背後に漂う静かな「死生観」に引き寄せられた。辺見さんはある映画を引き合いに出しながら、生と死を語った。
「ベニスに死す」(ルキノ・ヴィスコンティ監督、1971年)―。ドイツの文豪、トーマス・マン(1875―1955年)の名作を映画化したこの作品の舞台は20世紀初めのイタリア有数の観光都市・ベニス。感染症(コレラ)が蔓延するこの地を初老の音楽家が避暑に訪れる。コレラ禍のうわさが広がるそんなある日、神のごとき美少年に出会う。体調がすぐれない一方で、少年に対する思いは逆に高まっていく。主人公はまるでスト−カ−みたいに少年の後を追い続け、死の影が忍び寄る街をさまよい歩く。やがて、病魔に侵され、少年の姿をまぶたに焼けつけながら、死んでいく。BGMは「エリ−ゼのために」。結局は実ることはなかったが、ベ−ト−ベンが心を寄せた若き貴婦人に捧げた曲だと言われる。
「(疫病下での)滅びゆく者の美しさ。風景全体をある種の美として描き切ったのが面白い」と辺見さんはポツリと言い、こう続けた。「あの風景の中には“人類はこうあるべき”とは違う、まったく“わたし”的な生き方がある」―。東日本大震災の際もそうだったが、いつの時代でも大災厄は個々の人間存在の根源そのものを問うてきた。今回、この名画を見直してつくづくとそう思った。「ニュ−ノ−マル」(新しい日常)という奇怪な“現象”は私にとっては、生と死を無化する陽炎(かげろう)ように見えてしかたがない。以下、印象に残った「辺見」語録(要約)を掲載する。
※
★「(コロナ禍のいまだからこそ)本当に表現したい。深呼吸しながら、し〜んと人間の存在を考える。未来が判然としない半透明の中で、手探りしながら…」
★「コロナ撲滅挙国一致統一戦線みたいだ。緊急事態宣言そのものが超憲法的で超法規的。歴史が暗転する時の警戒心がなさすぎる」
★「コロナで何が立ち上がったかと言えば、人間ではなく『国家』(像)が立ち上がった。このままでは日本が滅びる、アメリカが滅びると」
★「人間の英知は意外に進んでいない。いま必要なのはシンプルな平等感や正義感。コロナ禍の中で人間はもっと謙虚でければならない。集団で眉をひそめられる世間って、いやだな。うるせいって」
★「想像(フィクション)を超えて、リアリティ(現実)が無限に展開していく、否応のない不条理。それを表現しようと思っても、あらゆる言葉が陳腐になる。耳目が洗われる言葉…欲しいのは言葉だ」
★「科学だけではこの問題を解き明かし、深めるのは難しい。哲学も文学もあらゆることを動員して考えなければならない」
★「聖書世界を想起せざるを得ない風景がいまある。人間の終わりとか存在の終わりみたいな…。聖書を文学的にとらえる。アレゴリ−(寓意)が思考を深めるきっかけになる」
★「コロナ禍の特長は人間の無名化と数値化。個の営みを数値の中に組み込み、名無しの人間にしてしまう」
★「コロナに罹患すること自体があたかも負の価値みたいにとらえられている。たとえば、手洗いを励行しないなど現在のル−ルを守れない『悪』だとか」
★「アメリカのコロナ患者の半数は黒人かヒスパニックス。死亡率も何倍も白人より多い。根幹の問題は貧困。(コロナがあぶり出した)貧困はその人の責任ではない」
★「健康の義務化。不健康は自己責任みたいなコロナの『健康論』には怒りがない。コロナが教えてくれたものこそが、我われが暮らす社会の冷酷さではなかったか。こんなインチキな社会だったんだ、と」
★「(行動変容という表現に)まず、言語的にゾッとする。自動翻訳機で翻訳したいみたいで気持ちが悪い。この社会はこうも脆く、言語世界まで動揺している」
★「生活様式の変更を国家が指示するのはファシズム以上。その一方で(強権発動を待つ前に)民衆社会の基層部の劣化が進んでいる。私権を自ら制限していくという,たとえば『自粛』」
★「ニュ−ノ−マルが新しい優性思想に姿を変えるのではないかという不安。救われる者と救われない者との分断がされ、弱者がそのおびただしい死によって淘汰される。そんな予感の中をどう生きて行けばいいのか」
★「自分が生きる尺(しゃく)を今日一日に区切る。きょう一日分だけ。どこまで続くかわからない、毎日をやっていくしかないかなぁ」
《注 記》
●旧約聖書「コヘレトの言葉」
〜「なんという空しさ すべては空しい。かつてあったことは これからもあり、かつて起こったことは これからも起こる。太陽の下、新しいものは何ひとつない」
●堀田善衛(作家、1918―1998年)
〜「大火焔のなかに女の顔を浮かべてみて、私は人間存在というものの根源的な無責任さを自分自身に痛切に感じ…」(『方丈記私記』)
●アラン・シリト−(英国の労働者階級出身の作家、1928―2010年)
〜「風邪をひいても世の中のせいにしてやる」(貧困層の怒りを表現)
●スラヴォイ・ジジェク(1949年、スロバキア生まれの哲学者)
〜「(コロナ禍の三重の危機は)まず感染症そのもの、つぎは経済の破綻、そして精神の崩壊。(この事態を生き延びるための容赦のない措置として)人間の顔をした野蛮が正当化される(たとえば、恣意的なトリア−ジ=生死の優劣)」
●ジャン・ボ−ドリヤ−ル(フランスの思想家、1929―2007年)
〜「人間もウイルスみたいなもの。人間がウイルスを発見したのではなく、ウイルスが人間を発見した」
(写真は古典的な名画「ベニスに死す」の一場面=インタ−ネット上に公開の写真から)