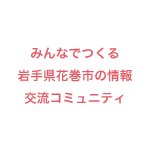「この分では日本国の一切が焼け落ちて平べったくなり、階級制度もまた焼け落ちて平べったくなる、という、不気味で、しかもなお一面においてさわやかな期待の感であった。あの頃に、空襲で家を焼かれた人々が、往々にして、歎き悲しむのではなくて、…『焼けてこれであたしもサッパリしました』とよく言ったのは、そこにやはり何程か異様な期待の感があったからではなかったろうか」(『方丈記私記』)―。作家の堀田善衛は鴨長明の『方丈記』に重ねながら、東京大空襲(1945年3月10日)に遭遇した時の気持ちをこう書いている。
東日本大震災の際、一方では口にするのを憚(はばか)りつつも私自身、内心では同じ気持ちを抱いたのも事実だった。「この災厄を機に開発至上主義の価値観は変更を迫られるだろう」とインテリの多くが語り、私もそう期待したのである。「戦争や自然災害などは風景を一変させるので、集団の記憶に残りやすい。これに対し、風景を変えない感染症は忘れられやすい」―。歴史学者で日本国際文化研究センタ−の磯田道史・准教授はこう話していたが、果たしてそうだったのか。「10年ひと昔」を前にして「3・11」はすでに忘却の彼方に押しやられ、「復興五輪」に日本全体が浮足立ったことは記憶に新しい。そして、それに待ったをかけたのが今回のコロナ禍だったという事実も何やら予言めいている。
「Black Lives Matter」(黒人の命「は=も=こそ」大切だ)―。こんなプラカ−ドを掲げたデモの隊列が世界を席巻(せっけん)している。全員がマスク姿である。米国における新型コロナウイルスの感染者は2百万人を超え、死者も11万人以上に達するなど世界で群を抜いている。しかも、黒人の死者は白人の2倍以上に及んでいる。そんな時、黒人男性が白人警官に殺されるという凄惨な事件が重なった。「風景」の背後に隠されていた人種差別や貧困のむごたらしさが未知のウイルスによって、その表皮がべろりと引きはがされたという思いにかられる。プラカ−ドには「警官はウイルスである」というスロ−ガンも。
「歴史的な英雄か、人種差別の象徴か」―。新大陸を“発見”したことで知られるコロンブス像の撤去や破壊など「白人至上主義」の歴史そのものにも矛先が向けられつつある。米国映画の名作「風と共に去りぬ」について、米国の動画配信サ−ビス会社は「奴隷制を懐かしむ場面がある」などを理由に急きょ、配信を停止する事態に至った。こうした波は欧州にも飛び火し、例えば英国では奴隷商人の銅像が引き倒され、海に投棄されるという事件も発生した。「コロナがあぶり出した社会の実相」が今後、「パラダイムシフト」(価値の大転換)の呼び水なるのかどうか…
「かつていったい誰が予感し反省しえただろうか。核爆弾の過剰とマスクの過少。それらが絶望的に併存する光景を…」(3月28日付「信濃毎日新聞」など地方紙配信記事「マスクとミサイル」)―。作家の辺見庸さん(75)はこう書いている。「マスクの過小」は感染症に対する危機管理の不在を浮き彫りにしただけではない。それはむしろ、“マスクデモ”が訴えかけるようなある種、文明論的な表象(シンボル)のような気がしてならない。堀田が、そして私自身が抱いた「期待」もたぶん、そんな感情だったのだと思う。しかしその一方で、私の心の片隅には「もうなるようにしかならない」という捨て鉢な心性も頑固に巣食っている。老い先が短いせいなのかもしれない。
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人とすみかと、またかくのごとし」―。『方丈記』は余りにも有名なこの書き出しで始まる。「世は常ならず」という“無常観”がひしひしと伝わってくる。「禍福は糾(あざな)える縄の如(ごと)し」―。諸行無常(しょぎょうむじょう)というやつである。
(写真はコロナ禍をきっかけにマスク姿でデモ行進する人たち=米ニュ−ヨ−クで。インタ−ネッ上に公開の写真から)