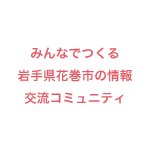「そういえば、今日は賢治の88回忌に当たる日だな」―。まんまるなお月さんを仰ぎ見ようと思い立った矢先、その命日を失念していた自分に粛然(しゅくぜん)たる気持ちになった。銀河宇宙を遊泳し続けた宮沢賢治にとって、「月」はいつもその心象風景のど真ん中にあり続けた。『月夜のけだもの』や『月夜のでんしんばしら』などの作品だけではなく、私はたとえば、『なめとこ山の熊』の次のような一節を無意識のうちに中天の「十五夜」に重ねていた。猟師の小十郎がクマたちによって、葬送される感動的な最終場面である。
「その栗の木と白い雪の峯々にかこまれた山の上の平らに黒い大きなものがたくさん環(わ)になって集って各々黒い影を置き回回(フイフイ)教徒の祈るときのようにじっと雪にひれふしたままいつまでもいつまでも動かなかった。そしてその雪と月のあかりで見るといちばん高いとこに小十郎の死骸(しがい)が半分座ったようになって置かれていた。思いなしかその死んで凍えてしまった小十郎の顔はまるで生きてるときのように冴(さ)え冴(ざ)えして何か笑っているようにさえ見えたのだ。ほんとうにそれらの大きな黒いものは参の星が天のまん中に来てももっと西へ傾いてもじっと化石したようにうごかなかった」―
「名月や/池をめぐりて/夜もすがら」(松尾芭蕉)、「名月を/取ってくれろと/泣く子かな」(小林一茶)…。「満月さん」というニックネ−ムで呼ばれた亡き妻を思う時、私は決まってのこの名句を思い出していた。しかし、今夜はどうもいつもと心持ちが違うようなのだ。「賢治なら、コロナ禍の地球をどんな思いで描写したのだろうか」―。そんな想念に突き動かされたからなのかもしれない。たまたまの偶然なのだが、明日(9月22日)が発行日となっている『ポストコロナの生命哲学―「いのち」が発する自然(ピュシス)の歌を聴け』(福岡伸一、伊藤亜紗、藤原辰史・共著)の中で、生物学者の福岡さんは賢治の代表作『春と修羅』(序)の冒頭に置かれた―「わたくしといふ現象は/仮定された有機交流電燈の/ひとつの青い照明です」という一節を引用して、以下のように述べている。
「『春と修羅』は、コロナ禍におかれた私たちが文明社会の中の人間というものを捉えなおす上で、非常に重要な言葉が書かれていると、私は思います。ここでまず注目したいのは、冒頭で『わたくし』は『現象』だ、と言っている点です。これは、『わたくし』という生命体が物質や物体ではなく『現象』である、それはつまり自然のものである、ということです。ギリシャ語の『ピュシス』は『自然』を表す言葉ですが、右に挙げた『春と修羅』の文章は、本来、生命体はピュシスとしてあるのだ、ということを語りかけているように思います」―。コロナパンデミックの謎を解く水先案内人が奇しくも賢治だという福岡さんの視点にぐいぐいと引き込まれた。
闇が濃くなるにつれ、雑草にすだく虫たちの声も一段と大きくなり、冷え冷えとした秋の風が体を突き抜けていく…。この日、イ−ハト−ブの夜空は分厚い雲におおわれ、8年ぶりに満月と重なった「中秋の名月」は時たま、気まぐれのように顔を見せるだけ。まるで“隠れん坊”みたいなその仕草が逆に、悪戯(いたずら)好きの賢治を彷彿(ほうふつ)させるのだった。それにしても…。命日の翌日に賢治からのメッセージが届くなんて、その”暗合(あんごう)”の妙に軽いめまいを感じたというのが正直な思いである。
(写真は雲間からひょっこり、顔を見せた「満月さん」=9月21日午後7時50分ごろ、花巻市桜町の自宅庭から)